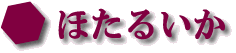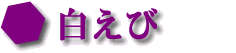|
|
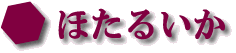 |
 |
| ほたるいかを最初漁獲したのは、天正13年(1585年)滑川の四歩一屋四郎兵衛という人であるといわれています。 また、あまり注目されなかったこのイカを、最初に研究した人は西川藤吉博士(1585年)で、当時西川イカと呼ばれていました。その後、明治38年渡瀬庄三郎博士が、ホタルのような光る珍稀なイカとして「ホタルイカ」と命名してから有名になりました。それでも当時、地中海沖合い発見された発行イカと同一視されていたが、大正5年石川千代松博士が別属、別種の新種として渡瀬博士の功績を記念し、ワタセニシア・シンチルランスと命名しました。 |
 |
| 日本海全域、太平洋側でも北海道以南から熊野灘にかけて分布するホタルイカだが集群が見られるのは3月末から6月にかけての富山湾だけだといわれる。近年相模湾、兵庫県沖、福井県沖でも獲れています。他に地中海のフランス沿岸、アフリカのマダカスカル島付近、中央アメリカの太平洋岸に僅か捕獲されるのが異種類ともいわれ、其の光力の大なること及び漁獲量も断然比較になりません。 |
 |
| ホタルイカの生態については、春から初夏にかけて産卵のために降雨や海のしける日を避けて、波静かな夜に大群で深海から浮上してくること、それも大方雌であるということが明らかです。ホタルイカの生息場所は水深300メートル前後で水温10度以下の海域に生息するとされています。これらはスケトウダラやクロゲンゲの胃に飲み込まれていたホタルイカからの推定であり、まだ十分に生息環境が解明されていないのが事実です。 |
|
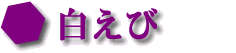 |
| 白えびは世界の珍味。富山湾のごく一部だけが、漁場となっています。河川の冷水が流れ込んでいる複雑な日本海棚の水深40mから200mの海底に生息している体長6cmから7cmの白色透明なえびで世界的にも珍しいえびの種類です。また、その色艶からベッコウエビとも呼ばれ年間捕獲量が少ないため高級で贅沢なものとされています。 |